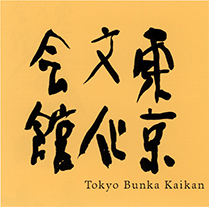お知らせNews
フェスティヴァル・ランタンポレル メッセージ
2024年09月30日 (月)
東京文化会館音楽監督・野平一郎 メッセージ
新しい音楽祭へようこそ
古典音楽と現代音楽のクロスオーバー
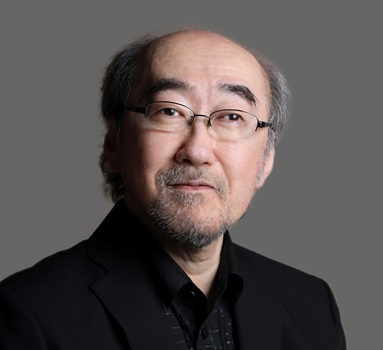
ランタンポレル L’intemporel とは、「時を超えた、非時間的な」という意味を持つフランス語です。要は特定の時代にこだわらないということですが、これを音楽の世界に置いてみるとどうなるでしょう。現在の音楽祭には大雑把に言って2つの傾向が見られます。現代音楽の音楽祭は、ますます専門化して一般的聴衆には近寄り難くなっています。一方で古典音楽のそれは限定された名曲を繰り返し演奏しているだけのものです。そしてこの2つにはまったく交わる点がありません。
この音楽祭では、こうした現状を打開すべく、2つの「ランタンポレル」を考えました。1つは現代に活躍する作曲家と、歴史上著名な作曲家のペアによるコンサート、もう1つは20世紀初頭の無声映画の名作に、現在活躍する作曲家が音楽を付けたシネマ・コンサートです。前者にはニームのレ・ヴォルク音楽祭、後者にはIRCAM(ポンピドゥー・センターフランス国立音響音楽研究所)と全面的に提携しています。
古典音楽の演奏も一捻り、レ・ヴォルク音楽祭の主要メンバーはピリオド楽器のオーケストラとして知られているレ・シエクルの楽員たちが中心。彼らは作曲家の時代にあわせた楽器の響きで、古典の楽器から現代の楽器までを自由に操ります。ピアノのリサイタルについても、1人が古典作品でのフォルテピアノと現代作品における現代ピアノを使い分けて演奏します。
フェスティヴァル第1回にあたる今年度は、レ・ヴォルク音楽祭の過去のプログラムから、ベートーヴェンとフィリップ・マヌリ、シューベルトとヘルムート・ラッヘンマンを取り上げます。この2人ずつの組み合わせに2回の室内楽コンサートと2回のピアノ・リサイタルがあり、フランスからお招きするレ・ヴォルク弦楽三重奏団と東京文化会館に縁の深い日本の演奏家たちが共演します。またピアノ・リサイタルには、今最も旬の若手ピアニストである阪田知樹さんと務川慧悟さんをお迎えします。
シネマ・コンサートでは川端康成原作、衣笠貞之助監督による無声映画「狂った一頁」と、パリで活躍する日本人作曲家平野真由さんとのIRCAMの最新音響を使った出会いをお楽しみいただきます。またナビゲーターとして沼野雄司氏が参加、解題を行います。
フランスからご招待するレ・ヴォルク弦楽三重奏団のマスタークラス、またその中心人物で音楽祭の芸術監督を務めるヴィオラのキャロル・ロト=ドファン、作曲家フィリップ・マヌリとのトークセッション等教育プログラムも充実しています。
ぜひこのレ・ヴォルク音楽祭・IRCAMと東京文化会館との緊密なコラボレーション「ランタンポレル」をお楽しみください。これまで存在しなかった一味違った音楽祭となること、請け合いです。
フィリップ・マヌリ メッセージ
ベートーヴェンの音楽と現代の関係とは?

彼(ベートーヴェン)は真の意味で音楽を近代に連れて行き、彼より前には人々が夢想すらしなかった場所に、音楽的構想を駆り立てていった。ブラームス、ワーグナー、マーラー、シュトラウス、シェーンベルク、バルトークに、さらにはシュトックハウゼンやラッヘンマンにすら、私には彼の音が聞こえる。フランス音楽は、このような次元で彼をとらえてこなかった。私が自分はフランスの伝統だけに属しているわけではないと感じるのは、おそらくそのせいだろう。
ベートーヴェンの思想で私をとらえて離さないものがいくつかある。第一に、音楽は絶えず進化し、刷新するものだと考えていることだ。音楽は——最も近代科学的な視野において——自然の反映であり、固定され、理想化されたイメージとは程遠い、絶え間ない変容なのだ。そして、理論的な厳密さと、あふれるばかりの直感的な想像力が絶妙に混合しているところにも魅かれる。他でもない彼本人が「大フーガ」のはしがきに 、「時には自由に、時には厳密に」と書いているのだ。私はいつもこの思想を私自身の作品で達成しようと努めている。バッハを聴くとバロック期を想起し、モーツァルトを聴くと古典派を、ベルリオーズを聴くとロマン派を思い起こすが、おもしろいことに、ベートーヴェンはいつでも、今現在ここにいる私に語りかけてくるような気がする。彼は非常に複雑な人物で、わずか5つの音符だけで主題を作曲し、そこから先例のない豊かさをもつ帰結を引き出した。聴覚を失ってなお、彼には未来の全貌が見えていたのか!いや、別の見方をすれば、未来は彼から自然に姿を現したのだ。
ヘルムート・ラッヘンマン メッセージ
5度映し出されるシューベルトのレンドラー
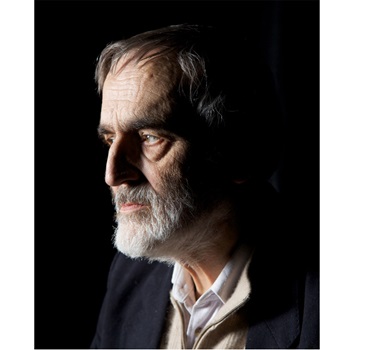
「シューベルトの主題による変奏曲」に関連して、私とシューベルトとの関わりは、と尋ねられると、私は少し困惑してしまう。恐らく「ディアベリ変奏曲」を作曲したベートーヴェンもディアベリという作曲家について、もしくは「パガニーニの主題による変奏曲」を作曲したブラームスや、シューマン、ラフマニノフもパガニーニという作曲家についてはあまり多くを語ることができないのではないだろうか。
子供の頃、私はシューベルトのピアノ曲が好きで毎日のように弾いていた。だが同じようにバッハ、ウィーン古典派のハイドンやモーツァルト、ベートーヴェンの音楽もよく弾いていたし好きだった。
「フランツ・シューベルトのレンドラーによる5つの変奏曲」は、私が20歳の音大生だった時の作品である。その頃私は馴染みのある音楽の世界をあてどもなくさまよい、シェーンベルク、ベルク、ヴェーベルンらの「新ウィーン楽派」にいら立っていた。私の音楽の世界像はヒンデミット、バルトーク、ストラヴィンスキーやドビュッシーで終わっていたのだ(シュトックハウゼン、ブーレーズ、ノーノ、ケージといったいわゆる前衛音楽やヨーロッパ外の音楽は、私にとってはただ遠くで閃いている稲妻のようなものだった)。
シューベルトの音楽から放たれるロマン派特有の深みや孤独といったものには当時は無関心で、私の目的はただ「変奏曲」というジャンルに習熟することだった。なぜなら、きっとそのジャンルで音楽の作曲上の構造や和声、モティーフの展開といったものに(恐らくドビュッシーがバッハの音楽について「アラベスク」だと称賛したものにも)意識を向けられると思ったからである。
私のレンドラーへの取り組み方はいわば子供のようだった。シューベルトによって作曲された音楽をおもしろいおもちゃのようにわくわくしながら観察し、同時に分解もしたのである。しかしまさにこの簡潔な遊びによって、私の作品に独自の表現が与えられることとなったのだ。
フェスティヴァル・ランタンポレル Festival de l’Intemporel
~時代を超える音楽~
2024年11月27日(水)~12月1日(日)
東京文化会館 小ホール
公演情報