前川國男に東京文化会館の設計が正式に依頼されたのは、1957年7月のことである。おりしも、直前の4月に、ル・コルビュジエのパリのアトリエから、1959年5月に竣工する国立西洋美術館の実施設計図9枚が日本に届いたばかりだった。だが、そこには設備や構造の図面は含まれておらず、建築も含めて、そのまま施工できる状態のものではなかった。そこで、坂倉準三と吉阪隆正と協議して、彼らに建築を任せつつ、前川は設備と構造の実施設計を担当することになる。こうして、師の建築の実現に弟子の3人が手弁当で協力する中で、歴史の偶然は、上野公園の向かい合う敷地に、図らずも、師弟の競演となる文化施設が相継いで誕生する機会を与えたのだ。
前川は、早速、1957年8月から東京文化会館の基本設計に取りかかり、1958年12月に着工するまでの15ヶ月間、超過密スケジュールの下、所員を総動員して設計を進めていく。費やされた延べ時間数は、建築だけで6万時間を越えたという。
東京都開都500年記念事業であり、戦後復興の象徴として、音楽界や演劇関係者からの熱い期待を受けての建設計画だった。そのため、求められたのは、本格的なオペラの上演が可能な舞台を持つ2300席の大ホールと国際会議としても利用される660席の小ホール、大小会議室と音楽資料室、140席のレストラン、リハーサル室や楽屋など、盛りだくさんの内容であり、延床面積は、西洋美術館の5倍の約2万1千㎡という規模になった。それでも、前川には、やり遂げる確かな自信があったに違いない。というのも、1952年の指名コンペで一等に当選し、1954年10月に竣工した神奈川県立音楽堂という実績があり、その手本となったロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホール(1951年)のデータを取得し、現地にも足を運んでいた。前川が11名の候補者の中から選ばれ、特命で設計依頼を受けたのも、日本建築学会賞を受賞した音楽堂の高い評価があったからだ。また、前川は、日本にはなかったオペラ劇場の仕組みや平面図についても、早くから文献資料を取り寄せて所員に調べさせていた。さらに、実施設計中の1958年5月には本場のウィーン国立歌劇場を視察し、2日間にわたって担当者から詳しい説明を受けるなど、周到な準備を重ねていた。
そして、こうした経験と調査から、前川が、ホールの舞台廻りの充実と共に、東京文化会館で何よりも重視しようとしたのは、聴衆が寄り集い、交流することのできるロビーやホワイエなど広いパブリック・スペースを確保すること、さらに、都市計画的な配慮によって、西洋美術館や南西側の日本芸術院会館(1958年,設計/吉田五十八)との良好な関係性を創出しつつ、周囲の環境との調和を実現させることだった。
こうして、大理石を埋め込んだ城砦のような厚い壁に包まれた大小ホールと、その外側に伸びやかに広がるロビーとホワイエ、西洋美術館と日本芸術院会館との間に取られた広いテラス、宙に浮いたようなレストランなどから構成される骨太で大らかな内外の空間が誕生する。それは、ホワイエやロビー、テラスの地下にリハーサル室や楽屋を埋め、上野の杜の大木のように林立する太い柱によって約7・4mの天井まで持ち上げられたお盆のような屋根の上に音楽資料室や会議室を載せるという、巧みな断面構成によってつくり出されたものだった。そして、師ル・コルビュジエに敬意を払うかのように、軒高とお盆の縁の高さを対面の西洋美術館に揃え、ガラス窓の縦桟の位置は西洋美術館の前庭に引かれた床の目地にあわせたのである。
東京文化会館は、戦後復興の息吹きが託された周到な計画と関係者の総力が見事に結実した稀有な施設として、フル稼働で60年にわたって音楽の殿堂であり続けている。それは、常にベストなコンディションで最高の演奏ができるようにと、その都度、適切なメンテナンスが地道に積み重ねられてきたからこそに違いない。竣工から20年が経った1981年、特徴的なコンクリート打放しの外壁の修復が本格的に行なわれ、赤味がかった透明な塗料でお化粧直しが施された。
1982年1月4日、NHKニュースで現地インタビューを受け、外壁の色について聞かれた76歳の前川は、「夕陽が当たって酔っ払いの顔がポーと赤くなったような感じの色にしようじゃないか」と指示したと答えた上で、次のように語っていた。
「私は、この建物は少なくともあと100年はもたしてほしいと思うんで、メンテナンスはその時々の方法を考えてやっていく必要があると思うんです。」
この発言には、東京文化会館に注いだ思いと、それを共につくり上げようとした音楽界や演劇界の人々、工事関係者、そして、この舞台に立った演奏家と聴衆、地道な維持管理を続けてきた東京都の関係者まで、多くの人々の気持を含んだ未来への願いが込められていたのだと思う。最後に、ささやかなエピソードを記しておきたい。この前川の発言の4ヶ月前の1981年9月11日、筆者は、大ホール1階8列31番S席の前川の隣で、日本初公演となるミラノ・スカラ座の演奏会、クラウディオ・アバド指揮のヴェルディのレクイエムを聴く機会があった。大のオペラファンだった前川は、美代夫人との鑑賞を楽しみにしていたが、大病を患っておられたので、若手所員が代わる代わる同伴することになったのである。開演前、2階の精養軒で、「僕はいつもこれに決めている」という早矢仕ライスをご馳走になった後、前川は、大ホール・ホワイエの窓越しに西洋美術館側のテラスを見つめながら、「このテラスはね、幕間に聴衆が歓談する場所として設けたんだけど、開館当初に壕を乗り越えて侵入した狼藉者がいたせいで、ずっと閉鎖されたままなんだ」と、独り言のようにつぶやいた。残念ながら、生前の前川はテラスの開放を見ることはなかった。しかし、今は形を変えてカフェとして使われているテラスの光景を含め、前川がこよなく愛した内外の空間も演奏会も、そのまま変わることなく、当り前のようにそこにある。
2016年、前川が実施設計に協力し、ル・コルビュジエ亡き後、その背後に新館(1979年)を増築した国立西洋美術館は、彼が世界7ヶ国で手がけた17件の建築群の一つとして、ユネスコの世界文化遺産に登録された。しかも、師弟の建築が仲良く対面に並ぶのは、世界中でここ上野公園だけである。そこには、ル・コルビュジエと前川國男が実現しようと志した人々の希望となる公共空間が生き続けている。前川が望んだように、その姿がこれからも大切に受け継がれていくことを願わずにはいられない。
Profile
松隈 洋(まつくま ひろし)
1957年兵庫県生まれ。1980年京都大学工学部建築学科卒業後、前川國男建築設計事務所に入所。
京都工芸繊維大学助教授を経て、2008年10月より京都工芸繊維大学教授。
専門は近代建築史、建築設計論。DOCOMOMOの日本支部であるDOCOMOMO Japanの2代目代表を務めた。
をご参照ください。
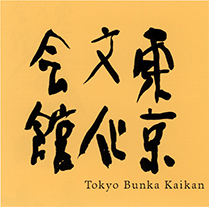















 音を響かせる雲形のパーツは彫刻家、向井良吉の作。
青緑黄色のシートが点在する客席はお花畑のイメージだとか。空席が目立たないという効果もあります。
音を響かせる雲形のパーツは彫刻家、向井良吉の作。
青緑黄色のシートが点在する客席はお花畑のイメージだとか。空席が目立たないという効果もあります。
 可動式でコンサート用舞台とオペラ・バレエ用舞台の入れ替えができる。
可動式でコンサート用舞台とオペラ・バレエ用舞台の入れ替えができる。
 ホールの入口は一面のサーモンピンク!高揚感倍増
ホールの入口は一面のサーモンピンク!高揚感倍増







 舞台の高さを調整できる。
特徴的な音響反射板とコンクリートの壁についている音を響かせるためのパーツは彫刻家 流 政之の作品
舞台の高さを調整できる。
特徴的な音響反射板とコンクリートの壁についている音を響かせるためのパーツは彫刻家 流 政之の作品
 ホール天井に吊り下げられた矢羽のような行灯型照明
ホール天井に吊り下げられた矢羽のような行灯型照明
 ホール裏の真っ赤な回廊
ホール裏の真っ赤な回廊