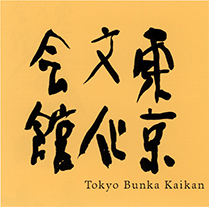News
Opera "Only the Sound Remains" Column (Details: Only in Japanese)
2021 May.31 (Mon)
東京文化会館 舞台芸術創造事業〈国際共同制作〉 オペラ『Only the Sound Remains -余韻-』
コラム
フェノロサとパウンドの夢 -能『経正』と『羽衣』のこと-
天野文雄(京都芸術大学舞台芸術研究センター所長)
およそ一世紀前の大正五年(一九一七)、ロンドンで`Noh’ or Accomplishment:A Study of the Classical Stage of Japan`が刊行された。それは東京美術学校の創設に尽力したことなどで知られる東洋美術研究家で、観世流の名手初世梅若実に師事して謡や舞の稽古をしたア-ネスト・フェノロサが生前にまとめていた能十一曲の翻訳(英語)を中心とした遺稿を、未亡人の依頼で若き詩人エズラ・パウンドが整理したものだが、この書はアイルランド出身の象徴詩人イエ-ツの詩心を触発し、イエ-ツに『鷹の井戸』など四編の舞踊劇を作らせたことでも知られている。
明治初年に来日し、観能の体験も豊富だったフェノロサに対して、パウンドは日本を訪れたことがなく能を観たこともなかったが、この書が象徴詩人イエ-ツに強く訴えかけたのは、イエ-ツと同じ芸術観をもつパウンドの「整理」に負うところが多かったらしい。その結果、その翻訳は能の本質を的確に捉えた「舞踊と吟誦の非模倣的な演技の芸術」(`Noh’ or Accomplishmentのパウンドの序説)として海彼に紹介されたのである。『Only the Sound Remains-余韻-』がフェノロサとパウンド二人の共同作業になる『経正』と『羽衣』の翻訳に拠ったのは、そのような舞台芸術としての能の把握に刮目したためであろう。では、能『経正』と『羽衣』はどのような作品なのか。
『経正』の舞台は秋の仁和寺。シテは西海で討死した平経正の亡霊。生前の経正は仁和寺の守覚法親王に寵愛された琵琶の名手である。法親王に仕える行慶(ワキ)が琵琶の名器青山〈せいざん〉を供えて弔っていると、深更、暗い灯火のもとに経正の亡霊が現われ、青山を奏で、仁和寺で過ごした風雅な日々を追懐して舞う。この間、経正の姿は行慶にはぼんやりとしかみえない設定になっているが、やがて修羅道の苦が襲ってきて、亡霊の経正の姿があらわになる。経正はそれを恥じて、灯火を吹き消して暗闇に消える。こうして、『経正』は琵琶をめぐる「懐旧」をテ-マに作られているのだが、そのテ-マを支えているのが、経正が弾く琵琶の音が仁和寺の松の葉音と交響するという情趣である。そこには「風に吹かれた葉の音が雨のように聞こえる」という白楽天の詩が用いられ、経正の亡霊は「夜遊の別れとどめよ」と思いを残して仁和寺をあとにする。作者は世阿弥の女婿金春禅竹(一四七〇年頃没)らしい。
一方、『羽衣』の舞台は三保の松原。漁から帰った白龍〈はくりょう〉(ワキ)が天女(シテ)が松の枝に掛けておいた衣をみつける。天女は白龍に懇願して衣を返してもらい、返礼に舞を舞って、地上に多くの宝を降らせ、春霞たなびく天上に消えるが、そこでは三保の松原から眺められる富士、清見関などの景観がさながら天上のようだと称えられる。天女の清麗典雅な舞と、天女による美景賛美を通して治世賛美を描こうとした作品である。天女が漁師の妻になったりして地上に留まるという羽衣伝説とは異なって、天女がすぐに帰天するのは『羽衣』の創案らしいが、その設定が『羽衣』をとりわけ清麗な作品にしている。作者は不明だが十五世紀後半には作られていた人気曲である。
すでに高い評価を得ている『Only the Sound Remains-余韻-』だが、このような能がどのようなオペラ作品に仕上げられているか、それはわれわれの期待だけでなく、一世紀昔にフェノロサとパウンドが待ち望んでいた夢でもあったのではないだろうか。
オペラ『Only the Sound Remains -余韻-』
2021年6月6日(日)15:00開演 東京文化会館 大ホール
公演情報
インタビュー・コラム
メディア掲載情報
関連企画:ワークショップ「カイヤ・サーリアホが描く音風景」
2021年6月1日(火)18:30開演 東京文化会館 小ホール
公演情報